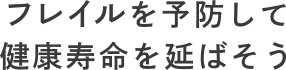厚生労働省が中心で「延伸」に取り組んでいる
健康寿命の延伸が必要な理由
少子高齢化によって生じる様々な課題
少子高齢化が進む日本においては、厚生労働省を中心に健康寿命の延伸を目的とした取り組みが進められています。具体的な目標としては、2040年に向けて健康寿命を男女共に3歳以上延伸、年齢にすると75歳以上にすることを目標としていますよ。詳細な内容は、厚生労働省が報告する「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部の取りまとめ」に記載されています。厚生労働省が健康寿命の延伸に力を入れている理由の1つは、今の日本が抱えている深刻な社会問題に関係しています。単に、社会通念上の目標としているわけではないんですね。では、どういった社会問題があって、なぜ平均寿命と健康寿命の差を縮めなければならないのかを知りましょう。
健康寿命の延伸が求められる背景
日本は少子高齢化が進んでいることは、ほとんどの人が知っているでしょう。2020年の調査によれば、日本における65歳以上の高齢者の人口は3,617万人で、前年に比べて約30万人も増加しています。総人口に対して占める割合も28.7%と非常に高く、日本人の4人に1人以上は高齢者というわけですね。また、高齢者の人口はこれからも増え続けることが予想されています。2040年には65歳以上の高齢者が3,921万人、総人口に占める割合では35.3%と、日本人の3人に1人以上が高齢者になるといわれています。
では、少子高齢化が進むとどういった問題が出てくるのでしょうか?少子高齢化によって、就業人口の減少、寝たきりの高齢者の増加、要介護者・重病者の増加などを招きます。その結果、現役世代の負担が増し、社会保障制度の持続も困難になってしまうんですね。事実、厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられるなど、現役世代にとって苦しい状況が続いています。
こういった少子高齢化が招く課題に対し、健康寿命の延伸は対応策の1つとして重要な役割を担います。健康寿命が延伸することで健康な高齢者が増え、それが医療費の負担軽減やシニア層の労働力確保、社会保障制度の持続可能性の向上などにつながるわけですね。健康寿命の延伸は、高齢者のQOL向上や健康格差の是正といった効果が見込めます。それも当然必要ですが、より深刻かつ危機的な社会問題が背景にあることは明らかです。それに対応するためにも、健康寿命の延伸が必須なんですね。
現在の具体的な取り組みとしては、健康無関心層へのアプローチの強化、地域・保険者間の格差の解消、疾病予防・重症化予防、介護予防、認知症予防、そしてフレイル予防などの推進が挙げられます。
今こそ読みたい!注目の情報はコレ!

今注目の介護予防資格
フレイル予防に携わりたい介護職におすすめの資格として、「サルコペニア・フレイル指導士」「介護予防運動指導員」「介護予防指導士」「介護予防運動トレーナー」を紹介します。ぜひ取得を目指してくださいね。